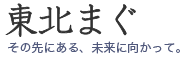冬をむかえた東北は、復興に向け熱い闘志を燃やしています。全編レポートの東北まぐ。第5号をお届けします。【東北まぐ!】
| 2011/12/11 発行 ※画像が表示されない方はこちらからご覧下さい | 配信中止はこちらから |


冷たい蔵王おろしが吹きつける12月の東北。山麓の農家の軒先では、あかく実った「紅柿」が薄皮をむかれて吊るされています。冷たく澄んだ烈風にさらされた柿は、渋味が抜け、甘く熟れた干し柿へと育っていきます。
寒い冬を迎える東北沿岸の街。失ったもの、足りないものは沢山ありますが、人々はこの冬を笑顔で乗り切ろうと静かに闘志を燃やしています。ここには新しいものを生み出す熱気と、始まる予感があふれています。
ぜひ、みなさまが新しい東北を訪れるきっかけとなる事を願って、「東北まぐ!」第5号をお届けします。
 福島交通のバスと、武藤泰典副社長
Information |
福島県民の足・福島交通 福島県内を走るバス会社「福島交通」。都市圏や相馬地区に路線を設けている、県民の足です。取締役副社長・武藤泰典さんにお話をお伺いしました。3月11日の地震では、乗客の安全を第一に直ちに運行停止。しかし、雪の降る寒い中、福島駅には帰宅できない人々がおり、バス20台を出し、暖房を入れて臨時の休憩所にしました。安全を確認し徐々に運行を再開。何より活躍したのが高速バス。東北新幹線は栃木県那須塩原駅止まりだった為、福島から那須塩原までの臨時バスを運行させました。1日6往復でしたが、震災直後関東と東北を結ぶ唯一の交通機関。1便に対し最大15台ものバスを出すほど乗客が殺到しました。武藤さんは震災以降3か月不眠不休の日々。 津波災害地区では、バスはケガをされた人、急病の人を病院へ運ぶ為に走りました。しかし、県内の観光地は大打撃を受けています。そこで福島交通は、1泊2日の復興ツアーを企画。1日目は被災地の現状を見て、2日目は福島県内の魅力を感じる場所を巡ります。来年1月頃には運行を開始予定です。観光地として戻る道のりは遠いけど、とにかく現状を見て欲しいと武藤さんは語ります。福島交通は県民には「ふっこう」と呼ばれ親しまれてきました。今度は「復興」への足として活躍していきます。 |
|
民間のボランティアセンターに 「こちらへどうぞ」と通されたのは、一軒家のあかるい和室でした。先客が数人、みかんが載ったちゃぶ台を囲むように談笑しています。会釈をすると「こんにちは。どうぞよろしく!」と、次々とあいさつが返ってきました。 この日、宿泊に訪れたのは、支援団体アースワンが運営するボランティアセンター「塩釡ハウス」です。地元の方から一時提供された家屋を利用し、県内外からやってくる支援者に向け、情報交換や宿泊場所として広く解放しています。我々が訪れた日の利用者は6人。石巻方面にボランティアに向かう男性のほか、仙台の復興イベントに出演する新潟の和太鼓奏者、気仙沼の飲食店再開を手伝う大学生など多彩な顔ぶれでした。「お互いに情報交換できてよかった」「学生時代の合宿みたいで、気持ちが若返った!」と感想も様々です。 運営者の杉浦恵一さん(25)も、県外からやってきた一人。現場で「ボランティアを求めるニーズはまだ沢山あるのに、ボランティアセンターはどんどん閉鎖されて行く状況を見て、”繋ぐ仕組み”が不足している」と感じた事から、自ら仕組み作りに乗り出しました。 「雑魚寝で良ければ、寝袋持参でご自由にというスタイル。利用無料でカンパを頂いています。シャワーと洗面、簡単な炊事ぐらいは出来ますよ」とスタッフの服部さん。 被災地と周辺地域の一部では、宿泊施設の確保が難しい状況が続いています。口コミながら利用者が徐々に増え、9月の開設から3ヶ月で100人を数えました。 「利用者に、細かい制限はあえて設けていない」と杉浦さん。「まずは現地の様子を知ってもらう事が大切」という信念のもと、ボランティアに限らず、被災地で開かれる復興イベントの県外スタッフや参加者、地域の方にも解放しています。 杉浦さんは「これからは力仕事以外の支援ニーズがどんどん増えていきます。例えば、各地で店舗や商店街の再開が始まっており人手が足りません。webを使った現地事業の支援やアート、音楽など、活躍の場は無限にあるはずです。とにかく長い目で応援して欲しい」と力を込めます。 |
 後列左から二人目が運営者の杉浦恵一さん。 この日同宿したメンバーで記念撮影。  壁一面に、ボランティア情報や応援メッセージ  敷き布団が足りなかったので、毛布を重ねて寝ました!
Information |

被災した水産業者が次々と廃業を決める中、老舗缶詰めメーカーが果敢にも会社の再建にのり出した。かろうじて柱と壁の一部が残された倉庫で、残骸に埋もれた商品を掘り起こし、事業復活に希望をつなぐ人々がいる。ふたたび人の行き交う街を目指して、復興へあゆみ始めた被災地。木の屋石巻水産の挑戦を通して、その長いみちのりを追いかけてみる。 (連載4回目、:前回はこちら)
 洗い終わった缶詰の選別を行う社員。 |
作業着姿の女性が、泥まみれの缶詰にゆっくりと手を延ばした。ボランティアのビブスを着た十数人の若者の眼が、食い入るように彼女の手の軌道を追いかける。女性はひと呼吸おくと、迷いなく目的の缶を拾い上げた。 お疲れー!やったね!周囲から拍手とともに歓声が上がる。いつの間にか出来た人の輪が、彼女を取り囲んだ。汗と涙で顔をくしゃくしゃにした彼女は、愛おしそうに缶詰を握りしめ「ありがとう、お疲れさまでした」と搾り出すようにこたえた。 |
|
8月3日の午後、4ケ月以上続いた木の屋石巻水産の缶詰の掘り起こし作業が、この瞬間をもって終了した。最期の一缶は、カンさんと呼ばれるボランティアの女性が拾い上げた。2ヵ月以上、毎日のように作業に参加してくれた彼女は、木の屋の社員にとっても戦友のような存在だった。 感動的な熱気に包まれた工場の片隅で、携帯電話を持って深刻そうに話し込む男の姿があった。社員の中村さんや鈴木さん、現場作業に出ていた木村さんの三人だった。受話器の向こうから、「あと500缶何とか出せませんか?」「先日話した物産展の件、あと1000缶どうしても必要です。お願いしますよ。」といった注文追加や催促の声がひっきりなしに聞こえてくる。 |
 新商品のサンプルを手に「ようやく出ました!」と木村さん
Information |
|
”希望の缶詰”として新聞や雑誌で取り上げられた木の屋の缶詰は、またたく間に話題となり注文が殺到していた。嬉しい悲鳴だが、洗浄作業が間に合わず希望に添えない。社員の木村さんは「せっかく注文を下さったのに、ただただ申し訳なくて」と、当時を振り返り言葉を詰まらせた。 秋も深まる頃、掘り起こした80万個近くの缶詰をすべて洗い終え、会社は新たな局面に突入した。「作業は”一区切り”ついたのですが、”終わった”とかいう感覚は全然ないんですよ。会社はまだスタート地点にすら辿り着いてない状況。まだまだ気を抜けない」と木村さんはいう。現在は協力工場の力を借りて、新商品の立ち上げと販売スタートに奮闘している。 「木の屋の皆さんが、安堵出来るのはいつですか」という問いに、商品開発の松友さんは「自社工場を再建して、また自分たちの手で商品を出せるようになった時ですよ」と力強く答えてくれた。(連載4回目) |
|
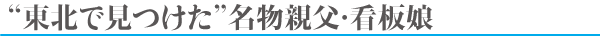
|
夕闇のせまる海沿いの街道に、「営業中」と書かれた小さな看板を見つけました。誘われるように小径をあがると、灯りのこぼれる物置小屋があらわれます。気温2℃、手がかじかむような寒さの中、 職人が一人ノミを握って作業に打ち込んでいました。「寒いのにようこそ。」手をとめて笑顔で迎えてくれたのは、すずり職人遠藤弘行さん(58)でした。 ここ雄勝は、600年の歴史を誇る全国有数のすずりの産地でした。3月11日の津波被害は甚大で、遠藤さんも自宅と作業場が跡形なく流されてしまいました。手元には二本のノミだけが残ったそうです。「好きで始めた職人の道なんで、辞めるという選択肢はなかった」という遠藤さん。「地産の良い石を使ったすずりを、少しでも安く届けたい」と直売にこだわり、物置小屋と廃材を組み合わせて、自宅跡に臨時の工房を再開しました。 震災後、全国のお客さんからたくさんの励ましや応援の注文が届き驚いたという遠藤さん。「すずりは、お客さんの手元に一生残るものだ」とあらためて気づかされたといいます。今日も港町の山裾に、石を削るノミの音が響きます。 |
 すずり職人の遠藤弘行さん(58)。 最高級の玄昌石にノミを入れます。 |
 工房も兼ねた、現在の”エンドーすずり館” |
Information |
|
岩手の銘菓と言えば何と言っても有名なのがモンドセレクション最高金賞も受賞した「かもめの玉子」でしょう。今回はこの三陸の銘菓「かもめの玉子」のゴージャスバージョン「黄金かもめの玉子」をご紹介します。 まず注目して欲しいのはお菓子の表面にちりばめられた金箔。これはもちろん本物の金箔を使用しています。実に豪華ですね~。 味は非常にクリーミー。しっとりとした上品な白あんとコーティングされているチョコレート、中に入っている大粒の栗とのバランスも良いですね。しっかりとした甘さですので、お茶請けとして緑茶にも合いそうですし、コーヒーとの相性も非常に良さそうです。また、デスクワークなどで疲れた時の糖分補給としても良いのではないでしょうか。気になった方はぜひお試し下さい!
Information |
 1個入りは350円  きらめく金箔と大粒の栗が豪華 |
配信中止はこちらから
メールアドレスの変更はこちらから
ご意見&ご感想はこちらから
編集長: 寺坂直毅
取材: 梅澤恵利子 岸田浩和
ゴチまぐ: 関 裕作
スタッフ: 野瀬紗也佳
発行元 :株式会社まぐまぐ
広告掲載をご検討の方は下記よりお問合せください。
http://www.mag2.co.jp/contact/adinfo.html
配送技術:株式会社アットウェア http://www.atware.co.jp/
「まぐまぐ」は株式会社まぐまぐの登録商標です
株式会社まぐまぐは、プライバシーマーク認定企業です
【東北まぐ!は、転載、複写、大歓迎です。】